デフレの原因として貨幣現象なのか、それとも需給のバランスかという議論があります。
様々な意見
貨幣現象という主張はアメリカの元FRB議長ベン・バーナンキ氏や内閣参与の浜田宏一氏など、いわゆるリフレ派が主張している理論で、通貨発行量によって物価が決まるという考え方です。
リフレ派の主張
たくさんあるものの価値は下がるという原理があります。例えばダイヤモンドは希少だから価値があるのであって、どこでも採れるのであれば、そこまで高価な鉱物にはならなかったでしょう。
お金にしてもアルバイトの時給が1万円の世界ではおそらく物価が高くなるはずです。簡単に1万円が手に入るのであれば、そもそも1万円の価値はそれほど高いものではないということになるからです。
なので、お金を発行すればデフレは解決するというのが、リフレ派の主張になります。その原理をもとに日銀は金融機関がもつ大量の国債を買い取って現金を供給しました。
一方で、需要と供給のバランスで需要が不足するために、デフレが起こると考えるのが需給バランス派の考え方になります。こちらはケインズが主張した理論です。
ケインズ派の主張
例えば、野菜が不作になると供給が不足して値段が上がります。逆に供給過多になると値段が下がります。つまり、需要が不足するためにデフレになったということです。
国内には家計、企業、政府という3つの経済主体があり、この3者それぞれに需要があります。家計は生活をするためにいろいろなものを購入しますが、所得の伸びが悪いので個人消費は減少傾向にあります。
企業はそういった家計の支出の動きを察知して、新たな工場や機械の導入を手控えています。新しい設備投資は一種の需要になりますので、ここが減ると物価が下がるというわけです。
また、政府も財政赤字を削減するために公共投資といった政府支出を削減しています。つまり、3者とも需要縮小しているので、それがデフレの原因というわけです。
本当の原因

では、どちらが本当のデフレの原因でしょうか?
実はこの二つの理論には少しずつ欠点があります。
リフレ派の欠点
リフレ派の主張するお金を発行すれば希少価値が下がってインフレになるという部分は、あくまで「全員にお金が供給されれば」という条件付きになります。誰しもが簡単にお金が手に入ることによって、お金の希少性が薄れるのです。
金融機関が大量に保有する国債を日銀が買い取って現金を発行したとしても、銀行や生命保険といった金融機関にお金が入るだけであって、預金者や国民に現金が支給されるわけではありません。
その点、バーナンキはヘリコプターからお金をばらまけばインフレになると、理屈に沿った的確な表現をしています。つまり、ヘリコプターからまくようにみんなにお金が行き渡ることが大切だと言っているわけです。
ケインズ派の欠点
一方の需給バランス派の理屈にも少しおかしいところがあります。昔は大根一本10円くらいだった時期もありました。現在では100円程度です。
インフレによって物価が上昇した結果ですが、需給バランス派の主張だと天候不順による不作で値段があがる場合と、インフレによる価格の上昇は本質的には同じということになります。
10円から100円に価格が上昇したのは、供給が減ったか需要が劇的に増えたことによるもので、昔に比べて大根が手に入りにくくなったことを表します。しかし、大根が手に入りにくいという話は聞いたことがありません。
価格はモノと通貨の価値を付き合わせて決定されます。大根が希少なら大根の価値が上がり、通貨が希少なら少ないお金で大根が手に入ります。リフレ派はお金の価値に注目して、需給バランス派はモノの価値に注目しているという点で実はそう本質的に食い違っているわけではありません。
リフレ派が有利
強いて言うならデフレは全てのモノの値段に影響することから、お金の価値が高まることで起こる現象といえるでしょう。つまり、リフレ派のいう通貨供給量の少なさがデフレを誘発しているということだと考えられます。
日銀の金融緩和は金融機関にはお金が供給されますが、国民の財布に入るわけではありません。大切なのはお金の希少性が薄れることですので、消費税の減税や財政支出の増大などお金がなるべく多くの人に行き渡る施策が必要です。流行りのベーシックインカムなどもデフレには有効だと考えられます。
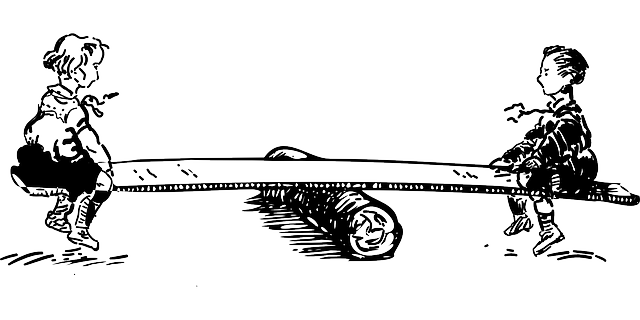
バズーカと揶揄された緩和策、日銀はこれまで紙幣をいくら供給したのでしょうか?その総額とは。
デフレ脱却への物価上昇策、具体的には政府が要請、指導するのでしょうか?
質問ありがとうございます。
黒田バズーカと言われるのは銀行や生保から国債を購入することです。2013年3月から2018年2月にかけて保有する国債の残高は125兆円→451兆円に増えており、326兆円の国債を購入したことがわかります。
日銀は年に80兆円を目標に国債の購入を行ってきましたので、ほぼ目標通りに国債を購入してきたことになります。ただし、リフレ派の主張するようなデフレ脱却はできませんでした。
日銀総裁は政府が人選して国会で承認しますので、就任した時点でデフレ脱却は大前提となります。
そういう意味では、総裁の人事そのものが政府の要請だということが言えると思います。
また、金融政策自体は金融政策決定会合で日銀が独自に判断して実行することになります。
参考
営業毎旬報告(日銀HPより)
2013年3月20日現在
(単位:千円)
<資産>
金地金 441,253,409
現金1 325,387,393
国債 125,052,720,521
コマーシャル・ペーパー等2 2,053,812,162
社債3 2,947,353,511
金銭の信託(信託財産株式)4 1,409,805,570
金銭の信託(信託財産指数連動型上場投資信託)5 1,515,303,563
金銭の信託(信託財産不動産投資信託)6 116,042,929
貸付金 26,010,167,000
外国為替7 4,978,103,984
代理店勘定8 68,041,803
雑勘定 467,898,382
合計 165,385,890,230
<負債および純資産>
発行銀行券 82,620,445,840
当座預金 43,817,720,361
その他預金9 315,687,477
政府預金 2,136,348,375
売現先勘定 29,838,899,809
雑勘定10 707,039,206
引当金勘定 3,237,012,172
資本金 100,000
準備金 2,712,636,985
合計 165,385,890,230
2018月2月28日現在
(単位:千円)
<資産>
金地金 441,253,409
現金1 258,097,744
国債 451,786,462,291
コマーシャル・ペーパー等2 2,301,406,350
社債3 3,279,784,397
金銭の信託(信託財産株式)4 1,035,849,431
金銭の信託(信託財産指数連動型上場投資信託)5 18,274,887,141
金銭の信託(信託財産不動産投資信託)6 459,562,323
貸付金 47,931,483,000
外国為替7 6,686,937,899
代理店勘定8 8,899,541
雑勘定 714,582,007
合計 533,179,205,537
<負債および純資産>
発行銀行券 103,706,575,073
当座預金366,704,433,419
その他預金9 19,830,078,544
政府預金 32,598,752,009
売現先勘定 166,914,813
雑勘定10 2,126,936,279
引当金勘定 4,860,982,590
資本金 100,000
準備金 3,184,432,807
合計 533,179,205,537